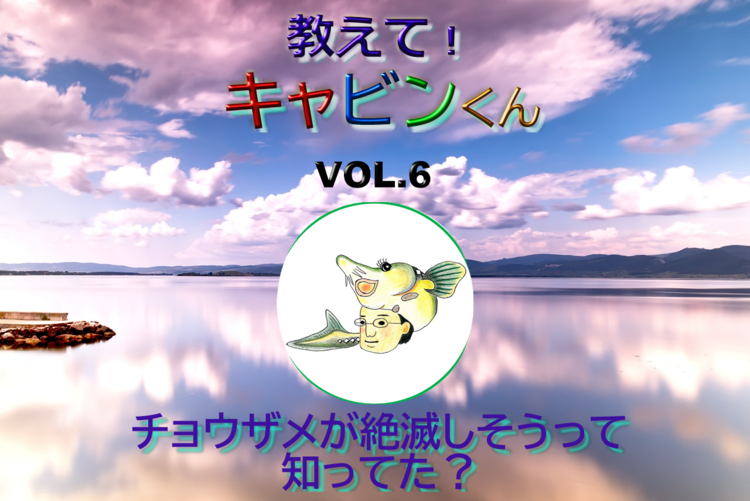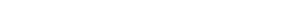Informationインフォメーション
【教えてキャビンくん】vol.6 ~チョウザメが絶滅しそうって知ってた?~
2022年7月、国際自然保護連合(IUCN)より更新された「レッドリスト」では、チョウザメ類の危機がより深刻さを増したことが明らかになりました。危機を招く要因は2つ。「高値で取引されるキャビア」と「流域管理の失敗」。
今回は野生のチョウザメ類を取り巻く、危機的な状況を深堀りします!
-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+:+:-:+:-:+:-:+:-:
キャラクター紹介
キャビア業界1年生!チョウザメ帽子をかぶって、日々お勉強に励むさめじまくん

キャビア業界1年生、同じくチョウザメについて勉強中。ちょっとファンキーなくぼさん

キャビア博士のキャビン・コスナー

キャビア博士のキャビーナ・ジョリー

-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+:+:-:+:-:+:-:+:-:
-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+:+:-:+:-:+:-:+:-:
今回のダイアローグ

今回はちょっと悲しいお知らせからお話しなくちゃならないんだ。

ギクッ!? なんだろう・・・、なんか胸騒ぎがするなぁ。

前回のお話の最後では、次回はチョウザメの漁獲拡大がどういう結果を生み出してしまったかを考える、って言ってたけど・・・。

そうなんだ、今回はチョウザメ類の絶滅に関するお話なんだよ。

ああ、聞きたくない、聞きたくない・・・

だめだよ、聞かなきゃ。これも勉強だよ。

2022年7月21日、国際自然保護連合(IUCN)は絶滅の恐れがある野生生物のリスト「レッドリスト」を更新したんだけど、その内容がね・・・。

全27種のチョウザメ類、そしてヘラチョウザメ類の3分の2が深刻な絶滅の危機にあって、すでに2種は野生の個体が絶滅してしまったという内容だったの。

ガァーーーーーーン

なんてことだ・・・。

今回、野生絶滅が確認された2種は、両方とも中国の長江に生息する固有種のヨウスコウチョウザメ(Acipenser dabryanus)と、ハシナガチョウザメ(Psephurus gladius)なんだ。

それにね、南ドイツから黒海へ注ぐドナウ川、中央アジアと東ヨーロッパの中間あたりに位置するカスピ海、そしてカザフスタンとウズベキスタンにまたがるアラル海に注ぐ大河川の流域で、チョウザメたちの減少や地域的な絶滅が確認されたわ・・・。

中央アジアやヨーロッパでも・・・。

そんなのってないよぉ~。チョウザメはさ、生きている化石なんでしょ?人類が誕生する遥か昔から、姿を変えずに、他の仲間たちがどんどん絶滅していっても、現代まで生き延びたのに・・・。

やっぱり、乱獲が原因なんですか?

それも大きな理由だね。前回、ロシア帝国ニコライ2世の頃からキャビアが高級食材として扱われるようになって、物凄いスピードでキャビア交易が増加したってお話したけど、それから約100年以上、乱獲が続いた地域もあったんだ。

ヨーロッパでも、生息している8種のチョウザメのうち、7種がレッドリストの最も絶滅危機の高いランク「CR:近絶滅種」に選定され、残りの1種も前回より危機レベルの高い「EN:絶滅危惧種」に選定されたの。

アラル海は、ほんの50年前までは日本の東北地方と同じくらいの大きさだったんだよ。

わぁ!東北地方と同じ!?

中央アジアのオアシス的存在で、かつては湖として世界第4位の面積を誇っていたの。

それが過去50年続いた無謀な灌漑農業によって、10分の1にまで小さくなってしまったんだ。

それはつまり・・・、アラル海の水を使いすぎて干上がってしまった、ということですか?

残念ながらそのとおり・・・。
そのことでチョウザメたちは見る見る姿を消し、アラル海に注ぐ河川で生息している3種のチョウザメも絶滅寸前の状態なんだよ。

なんだよぉ・・・、せっかくチョウザメのこといっぱい勉強してきたのに。おいら、悔しくって涙も出ねぇや・・・。

なにか具体的な対策は取られていないんですか?

チョウザメたちが激減してしまったことで、各国がキャビアの漁獲を禁止し、国際取引が規制されるようになってからも、キャビアは高値で取引されることから密漁や密輸(違法取引)が後を絶たないんだ。

なんじゃそりゃ。成す術なし、なの・・・?

さらに今回、チョウザメ類の絶滅と絶滅寸前の危機に追い込む大きな要因として強調されているのは、流域管理の失敗なの。

流域管理?それは何ですか?

さまざまな産業での水資源の利用方法や、開発の在り方を早急に見直して、国境を越えて流れる大河川の「流域」を、“一つのつながった自然”として捉えて保全していくことよ。

つまりね、チョウザメは海や河川を回遊する大型魚類で、時に川を1000キロも遡上して産卵するでしょ。だから、チョウザメという魚は沿岸域やそれにつながる河川、湖沼などの流域の自然が “つながった形” で維持されていないと生きていけないんだよ。

でも、近年は灌漑農業や工業、ダム開発などをはじめとする、さまざまな形での水資源の利用が各国で拡大して、河川や湖の水量が減少・枯渇して流域の各地が分断される事態が生じているのよ。この状況を「流域管理の失敗」と指摘しているの。

「流域管理の失敗」か・・・。

実際、黒海、カスピ海とその流域で生息するフナチョウザメ(Acipenser nudiventris)がドナウ川の中流域で絶滅して、EU圏内から姿を消してしまったわ・・・。

ああ、悲しすぎる。 EUは何か動いてないの?

うん・・・。ベルン条約などに基づく保全計画に意欲的な姿勢を示してきたけど、実際の状況は悪くなる一方でフナチョウザメだけじゃなく他の種でも、減少や地域的な絶滅が相次いでいるんだ。

うわぁー! なにか行動をしないとダメでしょ? なにか・・・、方法はないの?

今回ばかりは、さめじまくんの言う通りです。具体策を講じないと、もっと多くのチョウザメ類が絶滅しちゃいますよ。

今回ばかり・・・?

ぷっ

世界自然保護基金(World Wide Fund for Nature=WWF)のチョウザメ国際担当チームは、EU圏内で生き残っているチョウザメを保全するために、ヨーロッパ各国政府やEU機関が、全欧州での河川の連結性を回復し、主要河川のチョウザメ生息地で上流から下流を自由に移動できるようにする措置を含めた行動計画が緊急に必要だ、と指摘しているよ。

うぅ~~~ん。指摘や提言だけじゃなくて、実際に動き始めているのかな?なんだか、まどろっこしいな・・・。

確かに・・・。ただ、情勢や国益の異なる国々が、国を跨いで行動を一つにすることの難しさがあるのかもしれないね・・・。

分からなくはないけど、でも、そんなこと言ってる場合じゃないって気もするし。

一刻を争う深刻な状況には変わりないけど、今回のレッドリスト更新で、ほんの少しだけ朗報もあったの!

えええ~!? ほんとに?

なんですか?なんですか?

近年、ジョージアのリオニ川でフナチョウザメの生息が確認されるようになったんだ。

おお~っ☆

おお~っ☆

このことを受けてジョージアでは、リオニ川と黒海の沿岸でチョウザメの保護区を拡大したんだ。

これはEU圏内では姿を消してしまった、フナチョウザメを取り巻く環境を改善させる新たな一歩よ。

いいぞ、いいぞぉ~!

それに、地中海東部のアドリア海沿岸とその流入河川に分布していて、すでに絶滅したんじゃないか…と、言われていたアドリアチョウザメ(Acipenser naccarii)が、30年振りにイタリアで確認されたんだよ!

中央アジアのウズベキスタンを流れるアムダリア川流域でも、1996年以降記録のなかったアムダリアチョウザメ(Pseudoscaphirhynchus kaufmanni)が、2020年に再確認されたの!

北米大陸では長期的な保護活動が継続されていて、カナダのブリティッシュコロンビア州を流れるフレーザー川ではシロチョウザメ(Acipenser transmontanus)をはじめとするチョウザメの個体数が安定・微増しているという報告もあるよ。

そうこなくっちゃ~!ちょっとは明るい話もないと、気が滅入っちゃうよ~

そうよね!さめじまくんに元気がないと「ギョギョギョー!」も聞けなくなっちゃうし。

だめですよぉ、いたずらにさめじまくんを煽っては!

ギョギョギョー!

出た・・・。

ハハハハハ!
いま紹介した生息情報は、残念ながら保護活動の成果だけではなくて、ちょっとラッキーな偶発的な生存の確認によるものだけど、それでも、保護活動の強化によって個体数の回復に期待が持てることの表れでもあるよね。

例えばドナウ川でもロシアチョウザメの放流事業が行われているけど、こうした取り組みだけでは一時的な個体数の回復はあっても、恒常的な保全にはならないの。

ど、どうしてですか?

チョウザメ類がこの先も永続的に自然の中で生きられるかどうかは、水の流れのつながり、つまり「流域」の環境をいかに守れるかにかかっているわ。

国境を越えて流れる大河川の「流域」を、“一つのつながった自然”として捉えて守っていくことが大切なんですね。

それがチョウザメの未来を守るってことなんだな~。

健全な川と地域社会が共存し野生のチョウザメがたくさん泳ぐ未来を築くか、経済的利益に固執して何も手を打たずチョウザメのいない未来を迎えるか、すべては私たちの選択と行動次第、ということだね。

おいらはチョウザメのいる未来がいいな・・・。

ほんとだね。

みんなでがんばろう!

はい!

はい!
参考:WWFジャパン「2022年7月「レッドリスト」更新 チョウザメの危機が深刻に」ページ
-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+:+:-:+:-:+:-:+:-:
今回のまとめ
◎2022年7月22日に更新された「レッドリスト」では、全27種のチョウザメ類・ヘラチョウザメ類の3分の2が深刻な絶滅の危機にあると発表。
◎すでに中国長江に生息するヨウスコウチョウザメ・ハシナガチョウザメの2種については野生の個体が絶滅。
◎ヨーロッパでは生息する8種のチョウザメ類のうち、7種が最も絶滅危機の高いランクに選定。残り1種も前回より危機レベルがUP。
◎中央アジアでもアラル海の面積が8割消滅した影響で、3種のチョウザメが絶滅寸前。
◎危機の原因は「キャビア」と「流域管理の失敗」
◎高値で取引されるキャビアは国際取引が制限された以降も、密漁や密輸が横行し、乱獲が100年以上続いた。
◎「流域管理の失敗」とはチョウザメ類生息域の各国政府が、自国の河川を持続可能な形で管理できていないことを意味する。
◎黒海、カスピ海とその流入河川に生息するフナチョウザメがドナウ川中流域で絶滅し、EU圏内から消滅した。
◎チョウザメをめぐる状況は、悪化の一途をたどり続けており個体数の減少や地域的な絶滅が相次いでいる。
◎チョウザメの永続的保全には、国境を越えて流れる大河川流域を“一つのつながった自然”として捉え、河川の連結性を回復し、チョウザメが上流から下流を自由に移動できる環境を保全することが重要であり急務。