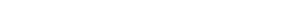Informationインフォメーション
【教えてキャビンくん】vol.5キャビアには女帝と鉄道が影響してるって知ってた?
古代エジプトからギリシャ・ローマと、紀元前の昔から人々に食べられていたキャビアとチョウザメ肉。しかし、歴史に名を刻む時の権力者たちに献上されてきたチョウザメ肉に比べると、キャビアの扱いは近代に至るまで実に低いものでした。
はたしてキャビアはどのようにして高級品へと変わっていったのか?変貌の道のりを歴史的背景から、ひもといてゆきます!
-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+:+:-:+:-:+:-:+:-:
キャラクター紹介
キャビア業界1年生!チョウザメ帽子をかぶって、日々お勉強に励むさめじまくん

キャビア業界1年生、同じくチョウザメについて勉強中。ちょっとファンキーなくぼさん

キャビア博士のキャビン・コスナー

キャビア博士のキャビーナ・ジョリー

-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+:+:-:+:-:+:-:+:-:
-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+:+:-:+:-:+:-:+:-:
今回のダイアローグ

前回は、チョウザメの魚肉について勉強したね!

いやぁ~、エジプト・ギリシャ・ローマと、古代文明の王や皇帝たちに献上されるほど高価で貴重な食べ物だったなんて全然知らなかったよ。

大きな壺一杯分のチョウザメ肉が羊100頭分以上の値打ちだったことにも、驚きました。

当時は漁業技術が乏しかったという側面もあるけれど、やっぱり美味しい食べ物だったということよね!
チョウザメ肉の栄養価の高さも重要ポイントよ。

「美味」「食感」「栄養」と、三拍子そろった三ツ星食材だもんね。

それにさ、チョウザメ肉とは対照的に、キャビアが庶民の食べ物で家畜の餌だったなんて、“おどろき桃の木、山椒の木”だよぉ~

例え、古っ…

え?え? なんか、言った?

あ… 確かに!私もそのエピソード、びっくりした~。

ぷっ

さっそく今日は、キャビアが食材としてどのように扱われ、その価値がどのように変わっていったのか、歴史的視点から説明したいと思うよ。

チョウザメ肉同様、キャビアも古くから食べられていたことは事実なの。
なんと、古代ギリシャで活躍した大哲学者で、その業績から「万学の祖」とも称されるアリストテレス(紀元前384~前322)が、キャビアについてコメントを残しているのよ。

アリストテレスか~!さすがにオイラでも名前は知ってる。

名前はね…

ああ、ちょうどいいわ!さめじまくんにアリストテレスの名言をひとつ贈ってあげる☆
「教育の根は苦いが、その果実は甘い。」

なにそれー?どういう意味ー?

つまり、勉強はつらく大変だけれど、それを乗り越えた先には大きな実りがあり、自らを豊かにする、という意味だよ。

ぬおぉぉぉー!オイラ、益々がんばっちゃうぞぉ!

さて、話をもとに戻すと…
キャビアが広く人々に食べられるようになったのは宗教的な理由が大きかったのよ。
988年、現在のロシア、ウクライナ、ベラルーシ辺りを治めていたキエフ大公国が国教をキリスト教(ロシア正教)としたの。
ロシア正教には肉・魚・卵・乳製品などの食物を制限する断食の習慣があるんだけど、それはこの地域の気候的な条件からすると、とても困難だったの。

そこで1280年、ロシア正教は正式にチョウザメ肉(魚卵含む)は断食期間中でも食べて良い食品と認めたんだ。
魚肉より魚卵の方が安かったから、たちまち農民たちにキャビアは食糧として広まっていったんだよ。大体バターと同じくらいの値段だったみたい。

ちなみに、元々チョウザメやキャビアは黒海の北側のアゾフ海やカスピ海周辺で食べられていたから、馴染みのある食べ物だったというのもポイントね。

ところで、いつごろからキャビアは高級品になったんですか?

それ、気になるよね!でも、まだもう少し後のことなんだ。

うぅぅ~、焦らすなぁ~

昔は食品の保存技術や輸送手段がかなり貧弱だったから、キャビアは塩気が強かったり、生臭かったりしたみたいなの。
ロシア皇帝からヨーロッパでの晩餐会やフランス国王への贈り物として献上されても、食べられずに捨てられちゃった…、なんてエピソードも残っているわ。

ひぃ~、もったいない!

キャビアがロシア以外のヨーロッパ諸国の王族や貴族に「美味しいもの」として認知され始めたのは、女帝エカテリーナ2世(1762ー1796)の統治時代なんだ。エカテリーナ2世が主催した豪華な晩餐会が契機とされているよ。宮廷料理人が腕によりをかけて用意したご馳走の真ん中に、ど~んっとキャビアが置かれたんだって!
真珠貝と金で作られたスプーンと共に、美しく盛り付けられたそうだよ。

それでロシア以外のヨーロッパ貴族たちも、キャビアに心を鷲掴みにされちゃったわけかー!

ロシア帝国最後の皇帝ニコライ2世(1894ー1917)の時代になると、シベリア横断鉄道の建設が開始され、先行していた西ヨーロッパの鉄道網が、ヨーロッパ全域の鉄道インフラとして整っていくの。そこへ冷蔵での輸送手段が開発されたことで、加速度的にキャビア交易が推し進められることになったわ。

キャビアの生産量から見るとその変化は如実で、1860年には4トンだった物が、1900年頃には3000トンとなり、その3000トンのキャビアを生産するために3万3000トンのチョウザメが捕獲されたんだ。
そしてロシアで生産されるキャビアの、実に25%がヨーロッパへ輸出されたんだよ。

結果として、ヨーロッパ全域にキャビア市場が構築されたことがキャビアの価格を高騰させた最大の理由であり、その価値を一気に高級品へと押し上げた…、というワケ!

なるほどなぁ~。ヨーロッパ全域に関わる、ものすごいスケールの話だったんだね~。

古代エジプト、ギリシャ、ローマから、ロシア帝国最後の皇帝に至るまで、壮大なチョウザメとキャビアの話だったなぁ。

これでも、だいぶ割愛しての説明だったけどね。

いやいや、ボリュームたっぷりだったよ。お得意のギョギョギョ!を挟む隙すら無かったもん・・・。

あっ、確かに!

無くてもいいんだよ。そもそもパクリだし…。

あぅっ・・・

ぷっ

さて次回は、その後に起こるチョウザメの漁獲拡大がどういう結果を生み出してしまったか、考えていきたいと思うよ。

はい!

がんばります!
-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+:+:-:+:-:+:-:+:-:
今回のまとめ
・チョウザメ同様キャビアも古くから食されており、古代ギリシャの哲学者、アリストテレスがキャビアに関する記述を残している。
・1280年、ロシア正教では節食期間中でもチョウザメとキャビアを食べてよいと公式に認めた。
・当時のキャビアの値段はバターと同等であった。
・ロシアのエカテリーナ2世の統治時代になるまで、ロシア以外のヨーロッパではキャビアは好まれていなかった。
・ニコライ2世の時代になると、鉄道網や冷蔵輸送の発達によりキャビアの輸出が急増する。
・ヨーロッパでの急激なキャビア市場構築が、キャビアが高級食材となった最大の理由。